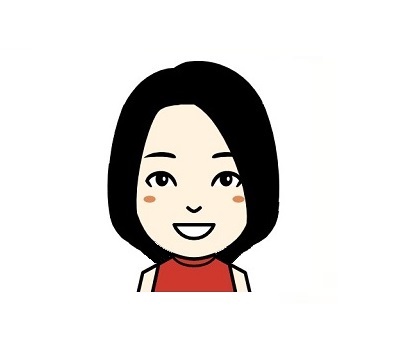一昔前であれば、先祖のお墓に自分も入って、と言ったケースが多く見られましたが、最近は「散骨」や「樹木葬」なども身近によく聞こえるようになってきています。
今回は、身内が亡くなったあと、本人の希望どおりに残された家族が弔ったとしても、それが一概にすべての方に受け入れられるものではなく、生じる問題などについてご紹介したいと思います。

近年は直葬や家族葬など葬儀の簡素化が進み、埋葬方法も遺族が区画を用意して建墓し管理や供養を行う「一般墓」ではなく、粉末にした骨を海や山などにまく「散骨」や墓石の代わりに樹木をシンボルとする「樹木葬」などが流行していますね。
女性の場合は、死んだあとも義父や義母と一緒にいるこは我慢できないと、嫁いだ先の家の墓に入ることを拒否して自分らしく弔ってほしいと望む方も増えていると聞きます。
しかし、著書『自分らしい逝き方』を書かれた日本葬祭アカデミー教務研究室代表の二村祐輔氏は、最先端の「シンプルな弔い」が失敗や間違いを生むことがあると指摘します。
葬儀において、『粗雑』と『簡素』をはき違えている人が少なからずおられるようなのです。
そもそも人間の死は社会的な出来事であるのに、“家族だけで見送るから”と亡くなったことすら親族のみにとどめて他人に知らせない傾向があります。
でもその結果、“なぜ教えてくれなかったの”“私はあの人を見送りたかった”と後日遺族へ苦情が届くトラブルも増えています。

親しかった友人が亡くなった場合に、亡くなったったことを知らせてもらえなかった場合、友人としてこれからどこで手を合わせたらいいのだろうかと悲しむ声もあります。
また、家族であっても同様です。
よく、後に残された家族の負担になりたくないからと『墓はいらない』『遺骨は海にまいてくれ』と主張する方がいますが、実際に亡くなった父親が望んだとおり海での散骨を終えた子どもたちが、『ぼくたちはこれからどこで手を合わせたらいいのでしょうか?』と亡き父の望みはかなえたものの、残された自分たちの弔う心はどこに持っていけばよいのかわからなくなるのです。
遺骨を粉砕してダイヤモンドに加工してアクセサリーを作る『ダイヤモンド葬』でも“小さなネックレスだからうっかりなくしてしまった”という問い合わせも少なからずあるそうです。
故人を思って手を合わせるには何かしらの対象(モニュメント)が必要です。
今まではそれが先祖代々のお墓でした。
しかし葬儀やお墓の簡素化が進んだ現代は、残された人の弔いの気持ちを持って行く場を奪ってしまっている可能性があるようです。
葬儀や墓は、家族や知人とのつながりを示すものであり、効率化を求めることが正解とは限りません。
埼玉県在住の主婦・Aさん(78才・仮名)のケースをご紹介します。
数年前にご主人が亡くなり、Aさんも終活にとりかかりました。
いちばん苦労したのはお墓をどうするかです。
Aさんは子どもたちの負担になってはいけないと、お寺と相談して墓じまいをすることに決めて実行ししました。
ところが墓じまいをしたことを伝えたら、『年に1回でもお墓参りすることでお父さんを偲べたのに、ひどい』と子どもたちから激しく非難され、墓じまいにかかった費用も額が大きすぎるとお寺にクレームを言ったりして、お寺との関係も険悪になってしまったそうです。
Aさんにすれば、自分のため、残された大切な子どもたちのためによかれと思って進めてきた「最期の準備」だったのですが、予想外の「立つ鳥跡を濁すこと」になってしまったのです。
自分が亡くなったあと、どのような弔い方を家族いしてほしいか、希望を温める半面、残される家族はどう考えているのかを、ゆっくりと話し合い、着実な方法でよりよい「その日」となるようにかんがえていきたいものです。

まとめ
それでもいつかは命を全うし、旅立った後には残された人たちがその死を悼み、思いをはせる「弔い」のときがやって来きます。
日々の忙しさに追われ、なかなかゆっくりと考える時間もないでしょうが、思わぬ虎ブウを避けるためにも、身近な問題として自分らしい「逝き方」を少しずつ模索していきましょう。