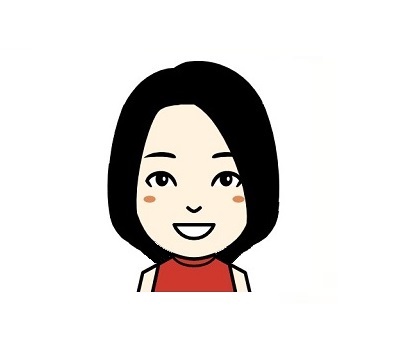福厳寺住職でYouTuberの大愚元勝さんは「ブッダは弟子たちに『話し方』に注意するよう口酸っぱく指導していたと言います。
下手な指導者は、感情に任せて部下を脅したりコントロールしようとするが、巧みな指導者は決して荒々しい言葉を使わない」とか。
今回は、佛心宗大叢山福厳寺住職でYouTubeチャンネル登録者数57万人を誇る大愚元勝氏著書『和尚が伝える 心が軽くなるブッダの言葉』より慕われる上司と嫌われる上司についてご紹介したいと思います。
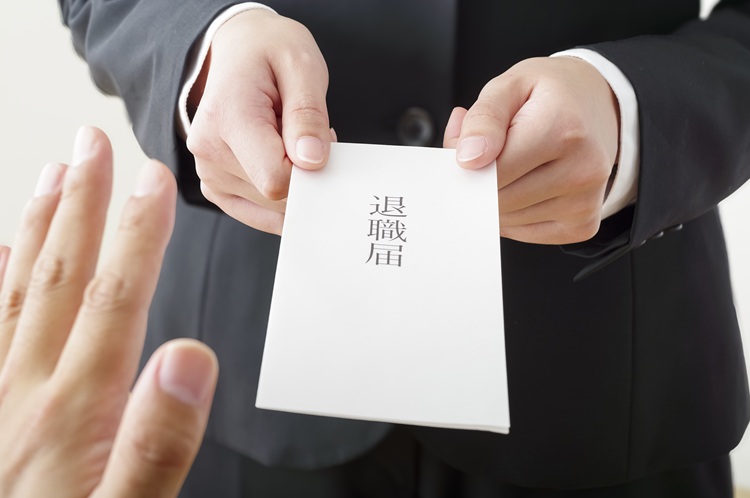
いつの時代にも、会社には2種類の上司がいます。
部下を育てられる上司と、部下を辞めさせる上司です。
もちろん様々な個性と人間性の部下がいますから、上司ばかりが責められるべきではありません。
それでもやはり、部下を育てられる上司と、辞めさせる上司がいるのです。
「給料に満足していない」「休みが少ない」など、部下はいろんな理由で会社を辞めますが、その背景には「上司が嫌い」という本音が隠れていることが多いのです。
残念ながら、部下を辞めさせる上司は、辞めた部下からも、まだ会社を辞めていない部下からも嫌われています。
当然ながら、部下を辞めさせる上司は、会社からも、上司として評価されません。
部下に嫌われる上司は自分の役割を分かっておらず、共通点があります。
インターネットで「部下を辞めさせる上司」とか「嫌われる上司」などと検索すると、嫌われる上司に共通する特徴がいくつも出てきます。
例えば、
・威圧的、高圧的
・仕事をちゃんと教えてくれない
・仕事を投げっぱなしでフォローしてくれない
・自分のミスをなすりつける
・自分の価値観ばかりを押し付ける
・自分が好きな部下ばかりエコひいきして、正当な評価をしてくれない
・偉そうな割には、公私混同
・感情的かつ陰湿
・説教時間が多くて長い
・異性として接してくる
・イヤミ、余計な一言が多い
・部下の言いなり
・自分の失敗を他人のせいにする
・部下の意見を頭ごなしに否定する
・仕事を任せてくれない
などなど。
実は、こうした上司の部下への接し方の裏には、上司自身が「上司として果たすべき役割」を分かっていない場合が多いのです。

仏教は、2600年もの永きにわたって受け継がれてきたブッダの教えですが、その歴史は、師匠が弟子を育成する営みの歴史であったと言っても過言ではありません。
いかに弟子を育てるのか。いかに人々を導くのか。
その問いがなければ、仏教はとうの昔に途絶えてしまったかもしれないのです。
それは会社でも同じです。
社員が育たなければ、会社の存続、繁栄はあり得ません。
だからこそ、上司は上司として果たすべき役割を理解し、上司としての「心・技・体」を兼ね備えていなければなりません。
では上司の「心」とは、どのようなものでしょうか。
仏教では、師匠が弟子を、僧侶が人々を導くことを「教化(きょうか・きょうけ)」と呼びます。
教化とは、「教導化益」の略で「徳をもち、正しいところへ手を握って連れていく」という意味です。
上司の役割は、部下の育成です。部下が立派に活躍できるように、教え導き、その能力や魅力を引き出してゆくことが「教化」です。
『六方礼経』というお経の中に、上司から部下への教化の実例が示されています。
『六方礼経』とは、ブッダが資産家の息子シンガーラに対して説いたもので、6つの人間関係についての極意が書かれています。
6つの人間関係とは親子、師弟(先生と生徒)、夫婦、朋友、労使(雇い主と使用人)、宗教者と信者です。
このうち、師匠が弟子に対する時の心得と、雇い主が使用人に対して接する時の心得が、上司から部下への接し方を考える上で、非常に参考になるので紹介します。
慕われる師匠(上司)に共通する5つの特徴
1.善く訓練し指導する
2.善く習得したことを覚えさせる
3.すべての学芸の知識を説明する
4.友人、同輩に弟子の善きところを吹聴する
5.諸方において、庇護(守って)してやる。
好かれる雇い主(上司)に共通する5つの特徴
1.その能力に応じて仕事をあてがう
2.食物と給料を給与する
3.病気の時に看病する
4.素晴らしい珍味の食物などを分け与える
5.適当なときに休息させる

次に、ブッダがより善い教化のために、弟子たちに奨励した「技」について紹介します。
その技とは、「話し方」です。
ブッダは弟子たちに、「言葉巧みであること」を奨励し、「分かりやすい言葉を使いなさい」「丁寧な言葉を使いなさい」と、口酸っぱく指導したと言われています。
下手な指導者は、感情に任せて、権力や暴力で脅し、外側から人をコントロールしようとします。
巧みな指導者は、忍耐強く、言葉と態度で理解をうながし、内側から人を導こうとします。
前者は短期的には効果的に見えても、長続きはしません。
指導者本人も、指導される側も疲弊し、ストレスや不満が溜まって病気になったり、爆発したりします。
後者は、少し時間を要するかもしれませんが、長期的に見て、指導者本人も指導される側も、なすべきことの意味を理解し、主体的に動くようになっていきます。
言葉を発する者が、どのような言葉を、どのような場面で、どのように使うかによって、受け取る者の、感じ方、考え方、行動が変わってしまうのですから、上司はよほど、使う言葉と、モノの言い方、伝え方に気を配る必要があります。
曹洞宗の開祖であり、福井の永平寺を開いた道元禅師は、『正法眼蔵(しょうぼうげんぞう)』菩提薩●四摂法(ぼだいさったししょうぼう)の巻で、以下のような「愛語」と呼ばれる言葉の使い方を説いています。
※●=つちへんに垂
「愛語というは、衆生をみるにまづ慈愛の心をおこし、顧愛の言語をほどこすなり。おほよそ暴悪のことばあり、不審の孝行あり。慈念衆生(じねんしゅじょう)、猶如赤子(ゆうにょしゃくし)のおもひをたくはへて言語するは愛語なり。徳あるはほむべし、徳なきはあはれむべし。(中略)むかひて愛語をきくは、表を喜ばせ、心を楽しくす。むかはずして愛語をきくは、肝に銘じ、魂に銘ず。しるべし、愛語は愛心より起こる、愛心は慈悲心を種子とせり。愛語よく廻天のちからあることを学すべきなり、ただ能を賞するのみにあらず。」
現代語に意訳してみましょう。
「愛語(親愛の情を起こさせる言葉)というのは、人でも動物でも、生きとし生けるものに対して慈しみの心を起こして、慈愛に満ちた言葉をかけることです。 決して荒々しい言葉を使ってはなりません。慈しみの念をもって、赤ちゃんに話しかけているかのような心持ちで話しかけるのです。 徳がある人には誉め、徳がない人には憐れんで戒めの言葉をかけなさい。 もしあなたが誰かに、面と向かって直接愛語を伝えたならば、その愛語を聞いた相手の顔はほころび、心も楽しくなるでしょう。 もしあなたが誰かのことを、面と向かわないで褒めたならば、人づてに、間接的にその話を聞いた彼、彼女は、『あの人がそんなふうに自分を褒めてくれたんだ』と、肝に銘じ、魂にジーンと深く刻み込まれるような感覚を覚えることでしょう。 よく知るべきです。愛語は愛心より起こり、愛心は慈悲心から生まれます。愛語には天を動かすほどの力があることを学ぶべきです。ただ相手の能力を褒めるだけが愛語ではないのです。」
この愛語こそ、上司が部下と接する際に基本としたい話し方です。
まとめるといったい上司はどのような「体」でいればいいのでしょうか。
それは、『自然体』です。
部下に威厳を示そうとして、偉ぶったり、威圧したり、カッコつけたりする必要はありません。
逆に、好かれようとして下手に褒めたり、おだてたり、ご機嫌をとったりする必要もありません。
褒めるべきは褒め、戒めるべきは戒め、ダメなこと、間違っていることはキッパリと指摘する。
上司だからと言って完璧を装う必要はなく、むしろ、上司であっても、失敗したり、間違ったり、迷ったりすることが自然ですから、それを隠す必要もありません。
自然体であれば、上司自身のストレスが軽減しますし、部下もまた自然体でいられるのです。

まとめ
仏教は、今から2600年の時を超えて受け継がれる、ブッダの教えですが、その教えには、慕われる上司の心技体が説かれています。
これらを参考にして、ぜひ上司としての「ありよう」を真似て実行し、誰もが慕われる上司に近づけてください。
「社員がすぐに辞めてしまう」 「部下に嫌われている」 「生徒に慕われていない」
もしあなたが上記のような雇用主、上司、先生などの立場で悩みを抱えているのであれば、このブッダの教えを読んで、上司としての自分を見つめ直してみてください。 きっと部下との関係が、目に見えて違ってくるはずです。