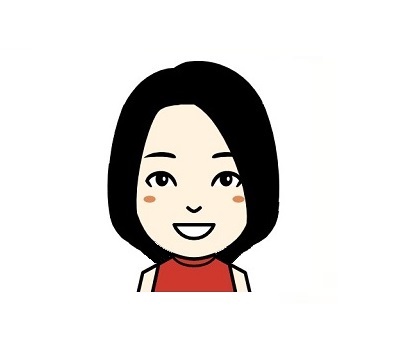今回は、新井紀子氏による著書『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』 の待望の続編となる『シン読解力』 から、教科書を正確に読み解く力=シン読解力と学力やビジネスとの関係について深掘りしていきます。
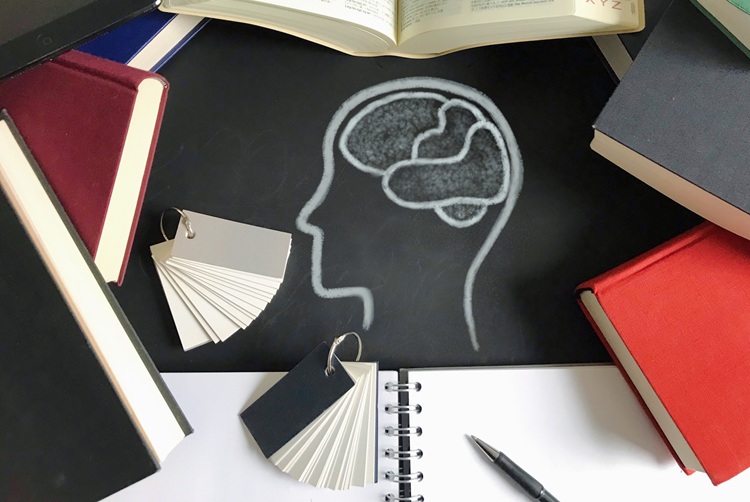
日常会話で使う「生活言語」と教科書で使われる「学習言語」とのギャップに、誰もが一度は戸惑った経験があるのではないでしょうか。
専門分野における難解な専門用語や構文は、苦労しますし慣れるのにとても時間がかかります。
そしてそれは中高生で出会う数学の証明の文章なども、『シン読解力』を読んで「数学語」なのだと感じました。
学生のときに、公式が理解できない、計算ができないのではなく、文章度読解時の独特な表現「ゆえに」「すなわち」などのにつまずいてしまっていませんでしたか。
これこそ数学に苦手意識を持ってしまうタイミングであるとともに、シン読解力に関わる「読み解く力」なだと思います。
『シン読解力』の中で、新井先生が「脳のワーキングメモリを無駄な活動に消費しないことが、本当に必要な情報を処理し、必要なときに取り出して問題解決にあたる上で重要」だと書かれていました。
ワーキングメモリとは、「情報を一時的に保持して操作する力」です。
単純な「短期記憶」とは異なる概念で、記憶を「使う」機能が求められます。
例えば、ワーキングメモリを測定する典型的なテストが、数字の逆唱です。
「6・2・9」と私が言ったことに対して、回答者が「9・2・6」という形で答える場合、「6・2・9」という情報を一旦頭に入れて、それを逆方向に入れ替えて出力する、まさに情報を一時的に覚えて、かつ操作するテストなのです。
こういった能力がまさにワーキングメモリなのです。
スマホの使いすぎが子どもたちの学力を「破壊」しています。
脳のメモ帳とも例えられる「ワーキングメモリ」を有効活用することで、学力アップにつながることは間違いないでしょう。

前頭前野とは、言語や論理的思考、感情の制御、共感や思いやりなどの機能を司る、いわば脳の司令塔のような領域です。
その前頭前野という領域が活性化するためには、たとえば本を読むとき、以下の2点注意するとよいでしょう。
1つ目は、本を能動的に読むことです。
本を受動的にぱっと眺めているだけでは、記憶には定着しにくいです。
読みながら自分の頭で内容や要点を整理し、問いを立て、理解を深めていく「能動的な読書」をすることが効果的で大切なのです。
2つ目は、読んだ情報のアウトプットをすることです。
大切なのは「入力」と「出力」をセットで行うことです。
読んだ内容をメモにまとめたり、人に説明したりする「出力」も記憶を強化するカギとなります。
これは「アクティブリコール」とも呼ばれ、記憶の定着を大きく高める学習法として知られています。
一度覚えて、それを思い出すということをセットで行うことで、記憶というのは強化されていくと言われています。
ですので、まず自分の中に入ってきた情報を整理しながら読み、自分の言葉に変換をしてメモに残せば「出力」ができます。
特におすすめなのは、一緒にいる人に本の内容を話してみることです。
読んでいるときはわかったつもりでも、説明しようとすると理解や記憶が曖昧で意外と言葉が出てこないことに気が付きます。
「出力」の練習を繰り返すことで、神経回路が強化され、読んだ本の知識が記憶に定着していきます。
『シン読解力』の中で新井先生は、音読や視写のトレーニングを取り入れることが、課題外在性認知負荷(=学習内容に取り組む以外で生じる認知負荷)を下げ、ワーキングメモリの容量を有効活用するために効果的だと書かれています。
ワーキングメモリがいっぱいになってしまうと、脳の中で情報がスタックしてしまうので、この「作業外の刺激をなるべく減らす」という指摘はまさにその通りだと思いました。
中でも音読は、脳科学的にも前頭前野を広く活性化する効果的な「脳トレ」であることがわかっています。
音読をしているときには、広範囲の脳領域が活性化します。
脳には、使うほど育ち、使わなければ衰えていってしまうという単純な性質があります。
脳の働きを維持するという意味で、音読は大人にとっても認知症予防などの観点で推奨されている方法です。
ワーキングメモリは、スポーツで言えばランニングや筋トレで鍛えるような基礎体力に当たる部分です。脳の基礎となる力を維持するためにも、音読はおすすめの方法なのです。

また、幼児期の絵本の読み聞かせが、語彙量のアップに効果的な方法だと紹介されています。
実は、脳活動の観点からも、読み聞かせは推奨されています。
読み聞かせを行うとき、読み聞かせをする大人の側では、単純な音読に比べて、脳の司令塔、前頭前野に大きな活動が生じることがわかっています。
また、読み聞かせをされる子どもの側では、言語発達にかかわる側頭葉や感情にかかわる脳領域などに活動が見られます。
それだけではなく読み聞かせは、大人と子どもの心の安定にも効果的なのです。
山形県長井市と私たち東北大学の共同研究から、8週間にわたって読み聞かせをしてもらうと、子どもの不安や抑うつなどの感情的な問題が減り、さらに問題行動が減るという結果が出ています。
さらに、読み聞かせ時間に比例して、保護者の育児ストレスも軽減されるという研究結果もあります。
読み聞かせは、言語能力を育てるだけではなくて、親子がよい関係を築くための親子の共同作業なのだということが研究によってわかったのです。
読み聞かせをすることで、子どもは新たな語彙と聞く力を身につけることができます。
さらに親御さんにとっても、育児ストレスが減って、育児が楽になります。
これほど多くのメリットがあるのなら、寝る前の5分だけでもやってみる価値はありますし、そう思っていただけたら嬉しいです。

まとめ
自分の「シン読解力」が足りないために、氾濫した情報を読み違えている可能性もあるわけです。
情報に振り回されないためには親子での「時間の共有」「体験の共有」「感情の共有」という「3つの共有」が大切で、それにより親子の共有から愛着形成が生まれ、勉強のルールや家族間のルール作りの基盤になります。
スマホの画面から目を離し、まずは目の前の子どもの目・顔・表情・姿・育ちに目を向けてみましょう。
それぞれの子どもの中にこそ、その子に合った最良のヒントがあるはず。
いましかない子どもとのかけがえのない日々を楽しみながら、小さな共有を大切にしていきましょう。