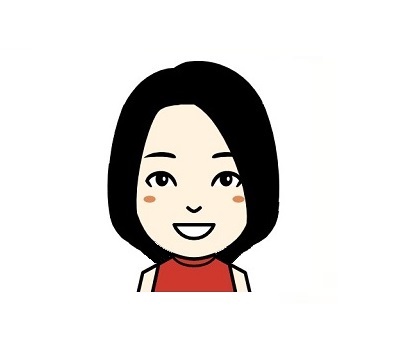仕事がめんどくさい。
風呂も歯磨きもめんどくさい。
もう、めんどくさいと思うのもめんどくさい。
みなさんもめんどくさいという感情を持つことが多々あると思います。
今回は、「めんどくさい」という感情はなぜ起こるのか、その本当の理由と克服法をご紹介します。

やるべきことが目の前にあるのに、なぜか動き出せないことってありますよね。
これは決してあなたの意志が弱いわけではありません。
実は、脳の働きによるごく自然な反応なのです。
人間の脳は、できるだけ少ないエネルギーで生き残るように進化してきました。
そのため、何か新しい行動を起こそうとするときには、それは脳にとってエネルギーを多く消費する「負担の大きい行動」になります。
すると、脳は「なるべく動かないように」と指示を出し、「あとでやろう」と先延ばしにしようとするのです。
例えば、ソファに座ってスマホを見ているときに、「部屋を片付けなきゃ」と思っても動けないのは、あなたが怠けているわけではありません。
脳がエネルギーを節約しようとする本能的な仕組みが働いているのです。
もう一つ、動くのがめんどうになる理由として、「脳の報酬システム」の働きが挙げられます。
脳は「すぐに得られる快楽」に強く反応し、長期的な利益よりも目の前の快楽を優先しようとします。
例えば、何かをする前に「動画を1本だけ見てからやろう」と考えたことはありませんか?
これは、脳が「今すぐ楽しめるもの」を優先してしまうためです。
目の前の娯楽(スマホ・テレビ・SNS)が、やるべきことよりも魅力的に見えてしまうのは、この報酬システムのせいなのです。
さらに、ストレスや疲労も「動くのがめんどう」と感じる原因のひとつです。
忙しい毎日を過ごすなかでは、脳は「まずは回復を優先しよう」と判断します。
その結果、行動するためのエネルギーが枯渇し、何をするのも億劫に感じてしまうのです。
例えば、仕事が終わった後に運動しようと思っていたのに、いざ帰宅するとソファから動けなくなるといった経験はありませんか?
これは、脳が「回復」を最優先しているために起こる現象なのです。
あなたが動くのがめんどうだと感じるのは、脳の省エネ機能や報酬システム、ストレスの影響が大きいのだということです。
では、具体的にどのような人が「動くのがめんどう」と感じやすいのでしょうか。
動くのがめんどうと感じる理由は人それぞれ異なります。
しかし、大きく分けると、いくつかの共通するパターンがあり、そのなかで特に多い3つのタイプをご紹介します。
タイプ1.エネルギー切れタイプ
仕事や家事、育児などで毎日が忙しいと、そもそも身体と脳のエネルギーが不足している可能性があります。
疲労がたまると、「やらなきゃ」と頭ではわかっていても、身体が動かないことがよくあります。
このタイプの人は、「動きたくない」のではなく、「動けない」状態になっているのが特徴です。
特に、以下のような傾向が見られます。
・休日になっても疲れが抜けず、寝てばかりいる
・帰宅後、何かをやろうと思っても結局ソファで動けない
・「やる気がない」というより「力が入らない」と感じる
こうした場合、無理に動こうとするのではなく、まずはしっかり休むことです。
質の良い睡眠をとる、短時間でも軽いストレッチをする、深呼吸でリラックスする。こうした小さな工夫が、次の行動につながります。
タイプ2.計画苦手タイプ
やるべきことが多すぎると、脳は情報を整理しきれず、フリーズしてしまいます。
この状態では、どれから手をつければいいかわからず、結果的に「めんどう」と感じてしまうのです。
例えば、部屋を片付けようと思っても、「どこから掃除すればいいのかわからない」となり、結局何もできないまま時間が過ぎてしまう。
こうした経験がある人は、このタイプの可能性が高いです。
このタイプに有効なのは、「最初のハードルを下げること」です。
「10分だけやる」「まずは机の上だけ片付ける」といった小さなゴールを作ると、動き出しやすくなります。
タイプ3.気分優先タイプ
「やる気が出たらやろう」と考える人は、意外と多いものです。
しかし、やる気が出るのを待っていると、いつまで経っても動き出せません。
これは、脳の「作業興奮」というメカニズムが影響しています。
作業興奮とは、「やる気があるから動くのではなく、動き出すことでやる気が生まれる」という現象です。
例えば、勉強を始めたら意外と集中できたり、運動を始めたら気持ちが乗ってきたりすることはありませんか。
つまり、このタイプの人にとって最も重要なのは、「やる気を出そう」と考えるのではなく、とにかく小さく動き始めることです。
立ち上がる、机に向かう、ペンを持つ。
こうした小さなアクションが、次の行動につながります。

では、実際にどうすれば「めんどう」を乗り越えて動き出せるのでしょうか。
以下で、すぐに試せる具体的な対策をご紹介します。
1.「5分だけやる」作戦
やる気が出ないときは、「とりあえず5分だけやる」と決めてみましょう。
これは、「作業興奮」の仕組みを活用した作戦です。
例えば、「5分だけ本を読もう」と決めて読み始めると、意外とそのまま続けられることがあります。
これは、「始めること」さえできれば、脳が動き出し、そのまま続けられる可能性が高まるためです。
もし5分経っても続けたくなければやめても構いません。
大事なのは「やり始めること」なのです。
2.環境を変えて脳をだます
人間の脳は環境に影響を受けやすいものです。
ずっと同じ場所にいると、脳が「ここはリラックスする場所だ」と認識し、行動を起こしにくくなります。
そこで、環境を変えると、脳のスイッチを切り替えやすくなります。
例えば、部屋のレイアウトを変えたり、BGMを変えたりするだけでも、行動のきっかけを作ることができます。
また、「家ではだらけてしまう」という人は、カフェや図書館など、外の環境を活用するのも効果的です。
3.「報酬」を設定する
「これを終えたら好きな飲み物を飲む」「片付けが終わったら映画を観る」など、自分に対して小さな報酬を用意するのも良い方法です。
人間の脳は「報酬がある」とわかると、行動を起こしやすくなります。
特に「短期的に手に入るご褒美」を設定すると、脳のやる気スイッチが入りやすくなるのです。
ただし、やる前にご褒美を与えてしまうと、逆にやる気が失われてしまうことがあるため、「行動したあと」に報酬を与えるのがポイントです。
4.小さな行動を習慣にする
「めんどう」と感じることを克服するためには、「動くことを習慣にする」のも有効です。
一度習慣になれば、脳が「これは当たり前のこと」と認識し、わざわざ意志力を使わなくても自然と動けるようになります。
例えば、歯磨きを「めんどう」だと感じることはほとんどないと思います。
これは、毎日繰り返すことで習慣になっているからです。
動くのがめんどうなときも、最初はほんの小さなアクションから始めて、それを習慣化することを意識しましょう。
最初は大変かもしれませんが、繰り返していくうちに自然と動けるようになります。

最後に「そもそもめんどうと感じにくい体質を作る」ための工夫についてご紹介したいと思います。
1.十分な休息と栄養を取る
「動くのがめんどう」と感じるとき、実は単純にエネルギー不足が原因であることも少なくありません。
疲れていると脳は「今は動くべきではない」と判断し、やる気を削ぐ信号を送ってしまうのです。
まずは、しっかりと睡眠を取り、バランスの良い食事を心がけることが大切です。
特に、鉄分やビタミンB群が不足すると、疲れを感じやすくなるため、食事に気をつけるだけでも体のだるさが軽減されることがあります。
2.適度に運動を取り入れる
「動くのがめんどう」と感じやすい人ほど、実は運動習慣が少ない傾向があります。
運動をすると、血流が良くなり、脳に酸素が行き渡ることで、気分がスッキリしやすくなるのです。
例えば、朝に軽くストレッチをするだけでも、脳が活性化し、1日のスタートをスムーズに切ることができます。
もし運動が苦手なら、散歩をする、階段を使うなど、小さな運動を取り入れるところから始めてみましょう。
3.生活のリズムを整える
生活のリズムが乱れると、行動を起こすためのエネルギーも不安定になります。
特に、不規則な生活を続けると、自律神経が乱れ、やる気が出にくくなることが知られています。
「朝決まった時間に起きる」「寝る前にスマホを触らない」「食事の時間を一定にする」など、基本的な生活習慣を整えるだけでも、行動のしやすさが変わってきます。
4.自分を責めすぎない
「またダラダラしてしまった…」「自分は意志が弱い」などと、自分を責めてしまうことがあると思いますが、 実は、このように自分を責めることが、さらに行動のハードルを上げてしまうのです。
人間は誰でも、「動きたくない」と思うことがあります。
大事なのは、「そういう日もあるよね」と受け入れつつ、小さな一歩を踏み出すことです。
例えば、「今日は何もできなかった」と思っても、「でも、机の上だけは片付けた」と、小さな達成を認めることで、次の行動につながりやすくなります。
まずは小さな行動から始めてみましょう。

まとめ
しかし、ちょっとした工夫をするだけで、行動しやすい状態を作ることができます。
いきなり大きな変化を求めるのではなく、「5分だけやる」「立ち上がる」「机に向かう」など、小さなアクションから始めることが大切です。
この小さな一歩が積み重なれば、「めんどう」と感じることが少しずつ減り、動きやすい自分に変わっていけるでしょう。
まずは今日、できることを一つだけでいいので試してみませんか?